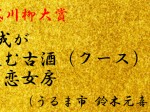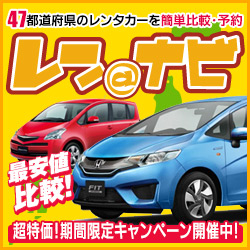【洋酒】年末商の小手調べ~売れゆきは“まあまあ”~(昭和47年9月15日)
-
[公開・発行日] 1972/09/15
[ 最終更新日 ] 2016/09/20 - 飲む
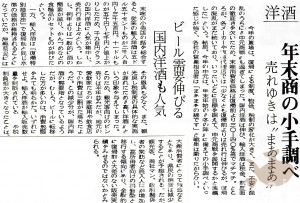 今年の夏場は、復帰による制度、物価、税制の変化が大きく、また、不安と混乱のうちに“中元商戦”も過ぎてしまった。国内洋酒は伸び、輸入洋酒は税金、制度面の徹底さを欠いたため、末端消費者価格は復帰前より30~40%高でマチマチ。
今年の夏場は、復帰による制度、物価、税制の変化が大きく、また、不安と混乱のうちに“中元商戦”も過ぎてしまった。国内洋酒は伸び、輸入洋酒は税金、制度面の徹底さを欠いたため、末端消費者価格は復帰前より30~40%高でマチマチ。
ところが、各メーカーや販売代理店では「少なくとも復帰前よりは売れ行きは伸びるが、復帰の混乱がまだ続いており、いったいどこに目標を据えて、中元商戦を展開するかと論議した」という。
結局、今年の中元は、年末年始の“冬の陣”に備えての小手調べといった感じが強く、各社の営業担当者は「まあまあの線です」と戦果は語りたがらない。
ビール需要伸びる~国内洋酒も人気~
末端の小売店の話を総合すると、従来の輸入洋酒は5ドル50セントものが2,800円~3,500円、11ドルものが5,000~7,000円と値上がりしたため、1,900円クラスの国内洋酒に人気が集中し、売れ行きは上々という。
しかし、例年よりは一般的に酒の需要が減り、缶詰などの食糧品のセットものが伸びたという。一方、輸入洋酒は「復帰特別措置法」で復帰前と同じ水準の価格が維持されることになっていたが、沖縄県民にはその恩典も少なく、また、観光戻し税制度の具体的な実施が遅れたため“高い洋酒”という印象を与えてしまった。
このため、観光客向けのピン売りは平年並みだが、地元の愛飲家たちの家庭用や飲食店での消費は3割がた落ちたようだ。この減少分が、国内洋酒の需要増となっているようだが、むしろ、ビールに転移した方が多いのは、消費形態をみても明らかだ。
いずれにせよ、輸入洋酒が輸入販売数量を制限されていることや、税制負担が大きくなったことは、大衆消費者にとって残念なことであり、県民の消費は減少することが予想される。
だが、観光客、商社マン、政府関係者の来訪など流入人口が増加し、高所得者向けの消費型と移行する傾向にあり、全般的に復帰前と大差のない販売実績をみせるのではないかとみられる。
関連記事
最近の投稿
アーカイブ
- open2026年(3)
- open2025年(25)
- open2024年(36)
- open2023年(53)
- open2022年(50)
- open2021年(38)
- open2020年(60)
- open2019年(66)
- open2018年(83)
- open2017年(109)
- open2016年(111)
- open2015年(56)
- open2014年(5)
- open2013年(38)
- open2008年(4)
- open2007年(12)
- open2006年(12)
- open2005年(11)
- open2004年(12)
- open2003年(12)
- open2002年(12)
- open2001年(12)
- open2000年(12)
- open1999年(12)
- open1998年(1)
- open1986年(1)
- open1980年(1)
- open1972年(56)
- open1971年(54)
- open1970年(45)
- open1969年(29)