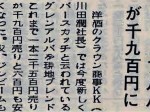昭和15~16年の京都の泡盛屋は、概して、つの型があったが、 これも大阪に本店をもつ大阪流の店構えで、今で云えばインテリアデザインといえないこともない。いかにも泡盛屋らしい店構えであった。
これも大阪に本店をもつ大阪流の店構えで、今で云えばインテリアデザインといえないこともない。いかにも泡盛屋らしい店構えであった。
巾二間半ぐらいのあまり広くない店、空色ののれん、白く琉球泡盛Θ支店と染めぬき麦には、琉球泡盛本場を銘打って、赤・黒字の大きな横看板もそして立看板も店の前に立てかけてあった。
店内に入ると壁の漆喰いが真新しい清潔さを誇張している。立ち飲みスタンド、(東京では椅子にすわって飲ましていたが、関西は立ち飲みであった。)が、ぐるりと曲って5~6坪ほどの店内を区切り、そのあせた素材の色に挑戦しているような白い裸体人形が便所の戸口の前も飾ってあった。
小鉢物などを入れるガラス箱の上に招きネコが5匹、大きい順に置かれてある。正面の壁には、かすれた墨で「酒は百薬の長」と書き、その横に朱字で「前金」と大きく記した額が客に見やすいようにかかげられていた。
スタンドの上には、サービス用の落花生や塩豆を入れた四角のガラスビンが2~3個置いてある。店の方では意地汚い客に備えて、サービス用の豆類をわざわざ塩水に浸し、ややかわきかけたのを客に出すのが、泡盛屋の秘訣でもあった。濡れた豆はポケットに入れたって、持っていきにくいからである。
しかし今は、塩豆などという昔なつかしいものは消えてしまったようだ。でも郷愁の残るただ塩辛いだけの豆であった。そのほか夏と冬には、季節のものをサービスしていた。夏は冷奴、冬はおでんの豆腐を船型の皿で出していた。1杯10銭の小さいコップを傾けるには、十分な肴であった。
それにしてもサービス満点のよき時代であったと云える。朝は6時から夜半過ぎまで営業していたのであるから、店の方も大変だったし、それだけ芭蕉の葉で包んだ蓋をした、縄しばりの南蛮甕から汲み出す泡盛を愛する人たちも多かった。客には貧富の差もなく、今の沖縄学の先進者たちや、弁当持ちの労働者たちでにぎわい、時には琉球民謡も流れた。
関連記事
最近の投稿
アーカイブ
- open2026年(5)
- open2025年(25)
- open2024年(36)
- open2023年(53)
- open2022年(50)
- open2021年(38)
- open2020年(60)
- open2019年(66)
- open2018年(83)
- open2017年(109)
- open2016年(111)
- open2015年(56)
- open2014年(5)
- open2013年(38)
- open2008年(4)
- open2007年(12)
- open2006年(12)
- open2005年(11)
- open2004年(12)
- open2003年(12)
- open2002年(12)
- open2001年(12)
- open2000年(12)
- open1999年(12)
- open1998年(1)
- open1986年(1)
- open1980年(1)
- open1972年(56)
- open1971年(54)
- open1970年(45)
- open1969年(29)