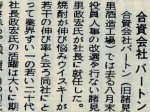今から26年前、初めて与那国島へ泡盛の取材に行った。国産のYS11機が就航間もない頃だった。高い運賃をどう工面したのか今もって解らない。11歳の次女由実と妻の2人に那覇空港から見送られ旅立った。飛び立って遥かなるまで2人がただ立っているのが、機の小さな窓から見えた。「きっとお土産を買って来るからね」と、心でつぶやいたものである。
与那国到着後すぐに久部良勇吉さん宅を訪ねた。赤瓦屋根の広い居間で取材は始まった。同島の酒造りの歴史は100余年前にさかのぼる。昔は島の東と西で各部落ごとに何か所という具合に造っていたという。大正15年にはあまりの重税に苦しめられ全業者が廃業。その後は那覇から船で運んできて売っていたという。
が、これがまた破損分まで課税されたため価格が高くなり、おまけに4斗積んだはずの酒が与那国に船が着くと3斗に減るという珍現象も生じたという。船客が盗み酒したのであろう。 業者は2進も、3進もいかなくなり、昭和2年に勇吉氏の父と満載名氏を中心に10人で酒造業を復活させ、去る大戦時まで続けたという。
敗戦後は1949年民営移管と同時に久部良勇吉、入波平信三、長浜靜一郎の各氏が免許を受け3酒造所で造るようになった。勇吉氏の工場は慶田元登、崎元順行の両氏と3人で各々仕込み場を持ち交互に蒸留した。歩留りも1対0.8が精いっぱいだった。
(以上は勇吉さんから聞いた当時の話である)
あの当時与那国島にあった泡盛は「稲穂」「どなん」「南泉」の3銘柄のレッテルで売られていた。県下全メーカーがそうであったように与那国もまた633㎖のビールびんの再利用であった。いうところの3合びん時代だったのである。当時、石垣島で9ドル余(100kg)の仕入値が与那国島に来ると14ドル余にはね上がり、したがって633㎖が小売り値40セントで売られていた。
話は最初にもどるが、宿は入福旅館という質素だがとても親切な宿であった。夕食のお膳には必ずコップいっぱいの泡盛が添えられていた。新鮮な魚料理は今でも忘れられない。そして色白で細面の宿のおかみさんも印象深い想い出となっている。 その宿には久留比という大阪出身の若い青年も同宿していた。
大学卒業後で、昆虫に詳しくここ与那国の蛾に興味があって、その観察に来たということだった。とても物静かな青年だったが、後日この男にはお世話になる事と相成る。
(1999年11月号につづく)
1999年10月号掲載