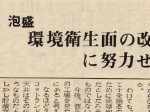【2004年9月号の続き】
つい今さきまで、わが沖縄の名酒、琉球泡盛を審査していた酒類製造の技術を指導している、 味覚に長けた先生方が目の前に居たのであった。沖縄が日本国に復帰した年に始まった泡盛鑑評会は、こういう専門家達によってあらゆる角度から厳密に審査され、そして欠点を見つけ出して指導をする御歴歴である。
味覚に長けた先生方が目の前に居たのであった。沖縄が日本国に復帰した年に始まった泡盛鑑評会は、こういう専門家達によってあらゆる角度から厳密に審査され、そして欠点を見つけ出して指導をする御歴歴である。
全く偶然であった。その中の幾人かは顔見知りであった。ここは飲み屋なんだから誰が居ようが何を飲もうが私には関係はない。
私が「ン?」と思ったのは彼たちみんなが飲んでいるのは泡盛ではなくウイスキーだったからだ。何だ一体このさまは。たった2~3時間前まで一般酒、古酒など何百点もの泡盛を審査して、その優劣を総括してきた専門家たちである。
“あんな不味い酒をいやというほど吟味してきたのだから、せめて疲れた舌をうまい酒で癒そうじゃないか”と、私には見えた。
私たち三人の顔を見た或る係官は、あわてて酒棚から自分で菊之露の720MLボトルを取ったが、時すでに遅しであった。その中には私と非常に親しく、沖縄在勤中はよく桜坂の小便横丁あたりでおでんをつつきながら泡盛を飲み、肩を組んで中通りを歩きながらバーの入り口に立っているホステスたちに小さな声で“泡盛置いてませんか”と聞き廻った間柄のS鑑定官の顔もあった。
私の鼓動は高鳴った。彼は私を見るなりコップ片手に微笑を浮かべて近づいてきた。久しぶりに出会う旧友と“いざ一献”という顔つきであった。次の瞬間私は踵を返してドアを開け、一人外に出た。下地潔さんたち2人の業者は、泡盛の直接の技術指導者たちの手前、おそらくは付き合ったのかどうかはその後ついぞ聞いたことはなかった。
Sさんとはよく馬が合った。彼の官舎でも飲んだし、私の家でも決して豪華ではない夕食を食べながら、おそくまで飲んで泡盛談義をした間柄であった。九州男児で気さくな性格であった。
小紙第51号(昭和54年4月25日付)の4面にSさんのあの時の“玉稿”が寄せられている。
今から26年も前のことである。私が40代の頃の事で、琉球泡盛はまだまだ気息奄奄(きっそくえんえん)の時代だった。桜坂や他の飲み屋街でも殆ど泡盛は置いていなかった。むしろ置いてない店ほど高級だという風潮さえあった時代だ。ホステスさんもしかめっつらして、“うちの店には置いてませんッ”だった。
それにしても私には一途なところがある。若かったあの頃がなつかしく思い出される昨今ではある。
Sさんの“玉稿”は次号あたりに全文掲載してあの時の横柄な態度をおわびしたい、と考えている。
ところで下地潔さんとのエピソードは尽きない。或る晩、桜坂の一流バーに2人で入った時、なぜかその店には泡盛があった。嬉しくなった2人は大きな顔をして飲んだ。相当酔いが回った頃、中央の大きなテーブルを囲んで飲んでいる6人位いの客が目に止まった。
その中に県庁のお偉いさんが居たからだ。これもまた泡盛ではなかった。昼間は盛んに“島産品愛用”(当時はそう称していた)を叫んで音頭をとっていながら夜はこんなものか。
私は我慢ならず酔った勢いで、とうとうテーブルを叩いて立って“一大演舌”をぶってしまった。慌てたのは潔さんであった。
・・・泡盛業界で初めて臭いのキツくない、おだやかな風味を造り出した下地潔さんが病に倒れた時、浦添市の総合病院に見舞って言葉を交わしたのが、彼との最後の別れとなった。
飲みながら楽しく語り合いができた昭和ひとけた生まれの泡盛製造業者が、また1人この世を去ってしまった。平成15年6月16日、享年74歳であった。さびしい限りだ。心からご冥福を祈るや切である。
2004年10月号掲載