あわもりやも10年ぐらいの年季が入ると味が出てくるのか、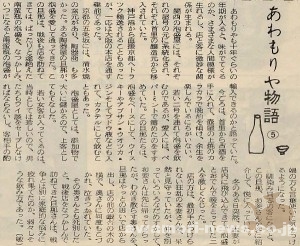 様々な人間模様が生まれるし、店と客に微妙な関係が生まれる。
様々な人間模様が生まれるし、店と客に微妙な関係が生まれる。
関西の泡盛屋には、それぞれの屋号の元に系統化され、それぞれ首里の醸造元から移入されていた。神戸港から直接京都へトラック輸送されることもあったが、一応は大阪の本店を通す建前であった。
京都の五条坂には、清水焼の窯元があり、陶器商も多かった。ある陶器屋の旦那が泡盛を愛して通ってきた。この旦那は、戦後も店を訪ねてきては、ばったりと途絶えた南蛮瓶の泡盛を懐かしみ、いつになると南蛮瓶の泡盛が輸入できるのかと語っていた。今頃は首里から古酒を手に入れて、壺屋の上焼のカラカラで晩酌を傾け、余生を楽しんでいるに違いない。
若い2号を連れて泡盛を飲むのであるが、愛人にはペパーミントで薄めたのを勧めていた。この旦那たちは、泡盛をベースにして、ウイスキーやアブサン、ウォッカ、ジンそしてブドウ液なども入れて、カクテルにして飲むこともあった。
泡盛屋としては、添加物で大いに儲かるので乗客としてもてなした。若い女客が入ってくるのは、当時としては珍しいので、男たちも猥談をセーブしなければならないし、客相手の酌婦の方も言葉使いに気をつけるようになった。馴染み同志の客になると、この旦那、お妾さんを客に紹介して悦に入っていた。
冬のある日突然、本妻が店内に飛び込んできて、泡盛とおでんで暖をとっていた2人を激しくなじった。店の方は、最初手がつけられない狂乱本妻さんを呆然と見守っていたが、仲を割って色々なだめすかして、お妾さんは先に帰ってもらったが、喚き散らす奥さんを、旦那さんはやっとの思いで店から出し、店の前の銀杏の木の横で奥さんに何度もこづかれ泣きつかれていた。
その奥さんとも死別したと、戦後店をなつかしんで訪ねてきた旦那さんは、戦争とは別に家庭的な悩みに疲れ果てたのか、弱々しそうな飲み方であった。
関連記事
最近の投稿
アーカイブ
- open2026年(5)
- open2025年(25)
- open2024年(36)
- open2023年(53)
- open2022年(50)
- open2021年(38)
- open2020年(60)
- open2019年(66)
- open2018年(83)
- open2017年(109)
- open2016年(111)
- open2015年(56)
- open2014年(5)
- open2013年(38)
- open2008年(4)
- open2007年(12)
- open2006年(12)
- open2005年(11)
- open2004年(12)
- open2003年(12)
- open2002年(12)
- open2001年(12)
- open2000年(12)
- open1999年(12)
- open1998年(1)
- open1986年(1)
- open1980年(1)
- open1972年(56)
- open1971年(54)
- open1970年(45)
- open1969年(29)






















